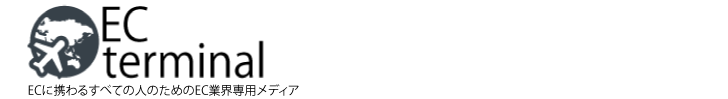今回はダイレクトマーケティング導入のメリット・デメリットと活用事例について解説します。
安定的な売り上げを確保するためには、いかに顧客と接点を持つかがポイントです。
様々なECサイトが存在する今の時代、ダイレクトマーケティングに注目が集まっています。
昔は良い商品を半場していれば勝手に売れることもありましたが、今はそうもいきません。
ダイレクトマーケティングで戦略的なアプローチを図って、有望な顧客リストを作ることで売上アップを狙っていく必要があります。
そこで今回は、ダイレクトマーケティング導入のメリット・デメリットと活用事例についてご紹介します。
ダイレクトマーケティングとは
ダイレクトマーケティングとは、企業が顧客と直接的なつながりを構築していくマーケティング手法です。
新聞やCMなどによる広範囲の人を対象としたマーケティングとは違い、顧客の反応やレスポンスを見て個々の顧客に対応します。
一昔前までは郵便などのリアルな現場でのダイレクトマーケティングが中心でした。
しかし、現在ではWEBを活用した手法が多く見られます。
ネットでもリアルでも顧客と直接つながれることで、顧客との信頼関係が築きやすくなり、顧客生涯価値を上げられます。
ダイレクトマーケティングの特徴
・顧客と良好な関係が生まれやすい
ダイレクトマーケティングは、顧客と直接交流を持つことができる手法です。
毎回自分に合った商品やメールが届くため、企業に対する親近感を抱きやすくなります。
適切な情報発信により信頼度を高まっていき、やがては商品の購買を考えるようになるでしょう。
・一人ひとりへのアプローチが可能
テレビや新聞を活用したマスマーケティングではできなかった、一人ひとりへの適切なアプローチが可能なので興味関心に沿った商品PRができます。
顧客の年齢や性別、購入回数に応じてグループを作成し、有望な見込み客へと育てていけるのです。
・双方向のコミュニケーション
顧客と直接的な関係でやり取りできることで、双方向のコミュニケーションが生まれます。
商品購入後にフォローアップメールを送ったり、キャンペーンDMを送ったりすれば無理なく広告できます。
住所や電話情報を収集していれば、ネットでもリアルからもアプローチできるので、情報を見てもらえる機会も増えるでしょう。
ダイレクトマーケティングのメリット
企業がダイレクトマーケティングを利用するのは、メリットが多くあるからです。
ダイレクトマーケティングを活用することで、収益化や販売の負荷を軽減できるでしょう。
・費用対効果が高い
今は、ユーザーの趣味嗜好や利用しているSNSが多様化しているため、商品に対してどの広告手段が適しているのかを見極める必要があります。
ダイレクトマーケティングでは、顧客の購入履歴やかかった費用などがストックされるため費用対効果が高く保てます。
商品を購入した顧客や関心のある顧客を分析し、適切なコミュニケーションを選択するので余計な費用を抑えられる点が特徴です。
・数字で明確な効果測定ができる
顧客と直接つながるダイレクトマーケティングでは、数字で明確に効果を測定できます。
商品の購入率やクリック率、レスポンス率などをデータで把握できるため、改善策が立てやすい点がメリットです。
たとえば、キャンペーンの広告DMに特典を付けて送付したとします。
実店舗に来店した時にDMを持ってきた人を測定すれば、地域や年齢など、どの層に影響があったのかを調べられるでしょう。
DMの送付により顧客情報を記録、分析、蓄積していけば、次回はさらにニーズに合ったキャンペーンが開催できます。
・収入の安定化
ダイレクトマーケティングによる初回購入で顧客情報を収集すれば、顧客リストが作れます。
顧客リストは言わば、これから見込み客になる人であり、自社商品を買ってくれる可能性の高い人たちです。
記録した顧客データをもとに、メールや郵送物を送っていけば効率的に営業できるため、不安定な収入に悩む心配もなくなるでしょう。
定期購入やサブスクリプションと組み合わせることで、安定収入を確保できます。
・少人数でも事業化しやすい
ダイレクトマーケティングの営業は、メールやDMを使って行います。
通常の営業活動のように人員を割く必要もないため、少人数の企業でも事業化しやすいのがメリットです。
抱えている顧客リストに定期的に情報発信していけば、売上げが上がっていくでしょう。
ダイレクトマーケティングのデメリット
ダイレクトマーケティングでは、顧客情報が記録されたデータをもとにDMを送付していけば、安定的な収入が確保できます。
ただし、導入にはデメリットもあるため注意しましょう。
・成果が出る前に時間がかかる
一定の顧客データを溜めるまでには、時間がかかります。
ダイレクトマーケティングは、個々の顧客に直接アプローチする手法なので、顧客リストがなければ始まりません。
新規顧客を獲得するための広告も考える必要がありますし、売上げアップの即効性には欠けます。
顧客データが蓄積された後も、レスポンスを確かめてPDCAサイクルを回していくことになるので、中長期的な視点での取り組みが必要です。
メリットが豊富はダイレクトマーケティングですが、すぐに効果が出ない点は理解しておきましょう。
・ターゲットに合わせて広告の見せ方を変えなくてはならない
新聞やCMなど大勢の人を対象としたマーケティングと異なり、アプローチでは顧客に合わせて広告手法や表現を変えなくてはなりません。
広告はターゲットに刺さらなくては意味がないので、年齢や職業といった属性に応じて最適な手法を選択するようにします。
たとえば20代や30代であれば、郵送物よりもWEB媒体の方が普段から馴染みがあり、見てもらえる確率が高まるでしょう。
広告内容もトレンドや興味関心を意識して、打ち出していかなければなりません。
ダイレクトマーケティングの活用事例
ダイレクトマーケティングは様々な業界で活用されており、知らないうちに利用している可能性があります。
他社や他業界のモデルを参考に、自社へ応用できる部分がないか考えてみるといいでしょう。
・金融
金融業界では、昔からダイレクトマーケティングが利用されています。
自宅にDMによるお得なキャンペーン情報を送付したり、ワンランク上の関連カードをご案内したりなどです。
カードローン会社では「今すぐの借り入れで手数料無料」などの広告をCMなどで流しています。
資料請求による顧客情報の獲得や見積もりサイトへの誘導といった例もあります。
・化粧品
化粧品のECサイトでは、DHCやオルビス、ドクターシーラボなどのメーカーが参入しています。
お試し化粧品をきっかけに、商品購入を促しているのを見たことがあるのではないでしょうか。
見込み客の獲得する目的で、サンプルを提供するケースもあります。
無料体験から定期購入へとつなげる手法が主流です。
・通信教育
通信教育としては、ベネッセやユーキャンが代表的な企業です。
新聞広告やチラシでのサンプル請求や無料教材の配布などがあります。
取得した顧客情報は、毎月の特典のお知らせなどに利用されています。
まとめ
ダイレクトマーケティングは、顧客への直接アプローチにより顧客の反応やレスポンスが確認できる手法です。
年齢や職業など蓄積された顧客データを調査・分析するため、顧客に自分に合った商品情報が届きやすくなります。
定期的なやり取りにより顧客との信頼関係が生まれ、効率的な販売が可能です。
ただし成果が出るまでには時間がかかるうえ、ターゲットに応じて広告表現も変える必要があります。
それでも定期収入や売上げアップが見込める点は、大きなメリットでしょう。
収入の安定化を目指している方は、事業にダイレクトマーケティングを導入してみてはいかがでしょうか。
コラム筆者
ECコンサルタント・アドバイザー
安田昌夫

- 東京都出身1984生まれ
- ECサイト運営歴10年で広告費をかけずに45万PVを達成
- 適切な集客・広告運用のサポート・無駄な広告費をカットするためのアドバイスを得意とする
- 月商1200万円突破