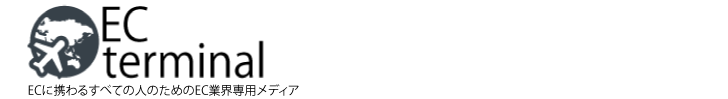新型コロナウイルスは社会に大きな影響をもたらし、それはEC業界も例外ではありませんでした。
消費行動が大きく変化した2020年を振り返ることで今後取るべき行動を決めることができます。
今回は、EC業界の2020年を振り返るとともに2021年のトレンド予測をしてみました。
2020年を振り返る
ご存じの通り、2020年は新型コロナウイルスによりEC業界は良くも悪くも大きな影響を受けました。
まずはEC業界の2020年を振り返ってみましょう。
2020年、売上を伸ばしたジャンルとは?
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために打ち出された外出自粛により、多くの人が家で過ごす時間が増えました。
そのため“巣ごもり”需要が増え、冷凍食品やレトルト・缶詰といった保存食の買い溜めや、マスクや消毒液、トイレットペーパーなどの買い占めが起こり、高額転売が始まります。
しかし、それらの商品は実店舗でも売れているようなものばかりで、「ECサイトならでは」といった商品ではありません。
ところが、4月に緊急事態宣言が発令されると様子は一変します。
人との接触を避けるため、急がない買い物は通販を利用するようにと、政府がEC利用を推奨したのです。
置き配やモバイルオーダー、オンラインキャバクラなど、さまざまな業界で非接触対応が進み、このころからECサイトでも変化が起こります。
EC化率の低い食品や家具といったジャンルで売上が急伸し、習い事や趣味といったイベントのネット化が進みました。
ID決済の普及
Amazonや楽天などの大手ではなく、認知度の低いようなECサイトにしかほしいものがなかった場合、クレジットカード番号の入力をためらうことも少なくありません。
しかし、ID決済ができるなら話は変わります。
Amazon payや楽天payに代表されるID決済とは、IDとパスワードだけで決済が行えるので、クレジットカード番号を入力する必要がありません。
ID決済の普及が進んだことも2020年の大きなトピックの一つといえるでしょう。
越境EC
新型コロナウイルスの感染拡大はインバウンド需要にも大きな影響を与えました。
入国制限により中国人観光客の“爆買い”に頼っていた小売業は大打撃を受けましたが、中国人の日本製品需要がなくなったわけではありません。
EC業界では2020年、そういった中国人向けに越境ECに取り組んだのです。
ただし、中国ではGoogle検索ができないため、「天猫(T-mall)」や「京東(ジンドン)」といったモールに出店することが成功につながりました。
2021年に予測されるトレンドは?
EC業界にとっても大きな転換期となった2020年でしたが、2021年におけるECトレンドはどんなものが予測されるのでしょうか?
オムニチャネル戦略がカギとなる?
オムニチャネルとは実店舗やECサイトなど、あらゆるメディアで顧客と接点を作ることで機会損失を防ぐ販売戦略です。
これまで、販売チャネルにECを取り入れる際、多くの企業はAmazonや楽天といった既存のプラットフォームを利用するか、自社ECを立ち上げるかの選択を迫られてきました。
しかし、スマートフォンなどから複数チャネルを行き来する消費者の動向に合わせるには複数チャネルを用意しておく必要があります。
自社ECはもちろん、大手ECプラットフォームへも同時出店するという手法が今後の売り上げ拡大につながると推測できます。
食料品のオンライン注文は定着する?
EC化率の低いジャンルの一つに挙げられるのが食料品です。
鮮度が重視される食料品は「実際に目で見て確かめたい」という傾向が高く、あまり普及してきませんでした。
ところが、コロナ禍により流れが変わります。
ネットスーパーの登録会員数が飛躍的に伸び、食料品をECサイトで購入することのハードルが下がったのです。
レシピと食材がセットになって定期配達されるミールキットなども市場拡大に役立っているようです。
食料品のオンライン注文が定着するかどうか、今後の動向が注目されています。
InstagramやYouTubeが購入きっかけに?
2000年以降に成人となった世代を指す「ミレニアル世代」の特徴として、複数チャネルを行き来する傾向が高いことが挙げられています。
中でもSNSが購買行動のきっかけを作ることが多く、重要性が増すものとみられています。
Instagramは商品そのものではなく“この商品を取り入れることで魅力的なライフスタイルになる”といった見せ方が得意なコンテンツです。
さらに自社ECとの連携が可能な「Shop Now」機能で購買行動を促すチャネルとして期待されています。
効果的に購買意欲を高められる、ライブコマースの場として期待されているのがYouTubeです。
ミレニアル世代から支持を集めるインフルエンサーを起用することで魅力的なコンテンツになることは間違いないでしょう。
Mコマースやボイスコマースが伸長する?
2020年、EC業界の躍進を語るうえで欠かせないのがMコマースです。
コロナ禍において、パソコンのある自宅で過ごす時間が増えたにもかかわらず、ECサイト利用の大半はスマートフォンなどのモバイル端末からによるものでした。
思いついたらすぐに操作できる、その利便性から2021年もMコマースの割合は増えると予測されています。
また、Amazon EchoやGoogle Homeといったスマートスピーカーを利用したボイスコマースも存在感を増してきています。
日本よりも普及が進むアメリカでは2022年には55%の人が利用するとの試算も出ており、その動向から目が離せません。
AIへの投資が進む?
業務の効率化に使われるAIはEC業界でも注目を集めています。
チャットボットなどのAIテクノロジーはページ離脱率の低下やコンバージョン率の上昇に役立ちますし、ユーザーの購入履歴や閲覧履歴から効率のいい商品紹介が可能です。
あるデータではECユーザーの20%がAIチャットボットから商品を購入しているとも出ており、2021年はAIテクノロジーへの投資が企業の明暗を分けるかもしれません。
グリーンコンシューマリズムが広がる?
地球環境問題に関心を持ち、配慮したサスティナブルやグリーンコンシューマリズムといった消費トレンドは以前からありましたが、購買方法に大きな変化のあった2020年、急速に広がりを見せました。
同様の商品であればサスティナブルな地球環境をうたったものを選ぶといった消費者心理は2021年も続くと考えられています。
その流れにいち早く乗ったのがAmazonです。
Amazonは2040年までに二酸化炭素排出量をゼロにすると宣言し、注目を集めました。
今後、追随する企業が増えていくことは容易に想像でき、サスティナブルやグリーンコンシューマリズムにどれだけ対応できるかが企業の課題となるでしょう。
仮想空間の活用が進む?
ARやVRで“体験”できるといった活用はこれまでにもありましたが、2021年はより仮想空間の活用が進むとみられています。
日本ではまだ導入されていませんが、Amazonはライブストリーミングを見ながらバーチャルガイドの案内で体験できるバーチャル体験型マーケットプレイス「Amazon Explore」を展開しています。
動画にはEC機能が組み込まれており、ショッピングのサポートもしています。
こういった仮想空間での体験を通じて購買チャネルを提供する手法は今後増えていくと予測されています。
今回は2020年の振り返りとともに、今後のトレンド予測をご紹介しました。
新型コロナウイルスによって思いがけない影響を受けたEC業界ですが、一過性のものとしてとらえるか、転換期ととらえるのかによって企業の成長速度は変わります。
今後はあらゆるサービスがEC化すると考えていく必要があるのかもしれません。
コラム筆者
ECコンサルタント・アドバイザー
安田昌夫

- 東京都出身1984生まれ
- ECサイト運営歴10年で広告費をかけずに45万PVを達成
- 適切な集客・広告運用のサポート・無駄な広告費をカットするためのアドバイスを得意とする
- 月商1200万円突破